体験を語る
- 避難所・避難生活
通信の重要性を痛感しつつも、多くの方の協力のもとで避難所を運営
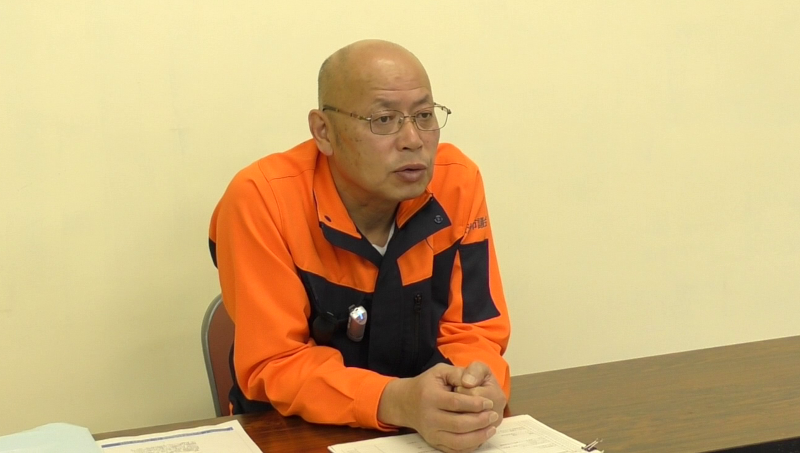
| 場所 | 珠洲市 |
|---|---|
| 聞き取り日 | 令和6年9月28日 |
地震発生当初
聞き手
最初に、町の被害状況、火災や建物が倒れたというところを聞かせてください。
川端さん
まず、火災はありませんでした。建物については、私は、当日は自宅におりましたけれども、自宅を出たら、すぐ隣のうちが倒壊して、道路を塞いでいましたので、通れません。反対側も、車で少し走ったところで、土砂崩れで通行不能という状況でした。周りの山からは、ミシミシとかバキバキという音が、ひっきりなしに聞こえて、恐怖を感じたのは覚えています。
聞き手
土砂災害はどうでしたか。
川端さん
山は最初、川の字のように崩れていましたが、日ごとに風雨があって、全面が崩れたような形です。
聞き手
道路の被害状況はどうでしたか。
川端さん
道路は、すぐには分からなかったんですけども、まず、輪島方面に向かっては、清水-仁江間でもう土砂が崩れていて、通れない状況でした。その道路を重機で開けてくださって、通れるようになっています。仁江から輪島方面に向けては、もう全然、土砂崩れで全く通れないような状況でした。大谷峠より国道249号も頂上まで行きましたが、頂上から下の道路が崩れていて、そこも通行不能となっております。あと、県道の上黒丸線も、東西地区、土砂崩れで最初に長期避難指示が出た場所ですけれども、そこは、もう道路を民家と土砂で塞いでいて通れない状況でした。
ただし、このとき、農道がありましたので、大谷のいわゆる、第二区、第三区のほうへは、そちらを通って行き来できるような状況でした。
聞き手
重機が来て通れるようになったのは、大体いつ頃ですか。
川端さん
2日か3日には。私は立場上、避難所の本部長でもありますけれども、当時は大谷分団の副分団長をしていて、停電、断水、通信も、SNSが一部、2日の途中ぐらいまで使えて、あとはつながらない状況でしたので、連絡網は、分団員による聞き取りで行っていました。仁江地区に取り残された分団員が2名いましたので、彼らが大谷のほうへ合流した際には、一応、道路は通行できたということになります。
避難所の運営について
聞き手
避難者の対応について教えてください。
川端さん
大谷公民館が指定の避難所になっていましたけれども、使えない状況でしたので、皆さんを大谷小中学校のほうへ案内しました。発災直後から2時間ぐらいは、高台に避難していて、皆さん、暗くなって寒くなってきたし、帰ろうとしたので、ちょっと待ってくれということで、学校へ行きました。通常時は、学校長とか一部の方しか学校の鍵を持ってないので、いざとなれば、ガラスを割るしかないなと思っていたんですけども、たまたま体育館側の出入口が、地震の影響で、鍵が開いていました。それで、何とか中に入れるということで、皆さんに声掛けして、そちらに入ってもらったわけです。
聞き手
公民館が使えなかったのはどうしてでしょうか。
川端さん
公民館は、もともと結構年数もたっている建物で、まず玄関の扉が2枚とも倒れていて、屋根の部分も損傷がひどくて、見た段階で、これは皆さんが避難するには使えないと判断しました。
聞き手
避難所の生活の中で、要介護者というか、お年寄りも一緒だったと思いますが、どう対応されていましたか。
川端さん
1日に体育館に入られてから、大津波警報がまだ出ている段階でしたので、もしかしたら津波が来るかもしれないと考えで、万が一、津波が来ても、3階で過ごしてもらいたいということで、要介護者、また、足腰の悪い方、高齢の方は、校舎の3階へ移動したんです。それ以外の方は、津波が来たら、また同じように高台に逃げるという心構えでいてもらいました。
聞き手
コロナやインフルエンザの対策はどうされていましたか。
川端さん
コロナが出た際は、旧の大谷中学校の2階の教室に隔離していました。出る際は、5日たっての経過を見ながら、保健師さんに検温もしていただいて、大丈夫ということであれば、翌日、また体育館に移動してもらうという形を取っていました。
聞き手
ほかの方は、みんな体育館のほうにいらっしゃったんですか。
川端さん
体育館がメインで、人数が増えてきた後は、1階の1年から4年生までの教室や多目的教室をお借りして、そちらのほうに、高齢者などは移ってもらいました。最終的には、そちらもコロナ感染者の隔離部屋になったりしています。最初のうちは、2階で、動線も完全にシャットアウトして、2階の方は2階のトイレを使っていただくという形で対応していました。
聞き手
トイレを分けていたのですか。
川端さん
そうですね。派遣の看護師さんも入ってこられてからは、そちらの指導を受けながら、排せつ物の処理をする際は、看護師さんが中心となって、防御服みたいなのを着ながら対応しています。
聞き手
避難所で、水や食料の備蓄はどう管理していましたか。
川端さん
一日に皆さんが入ってこられたときには、何もない状況でした。発災が1月1日だったので、暮れから子供が帰省していたので、食料もありましたし、そういったものや布団類を二日の日中に、うちへ帰って持ってきたりしました。食べ物については、自分たちの分のほかに、皆さんで使ってくださいということで出していただいたものもありました。
私自身は、3年前から群発地震がありましたので、消防の分団員という立場もあって、日頃から防災について比較的、どういう対応を取っていくべきか、考えていたんですけど、考えていた以上の災害でしたので、慌てました。
私は自営業でガス会社をやっているので、そういった何も使えない状況になったら、トラックにガスボンベと、コンロとガス釜を積んで行くということは、日頃から頭にありました。それと、正月でお米も30キロありましたので、それも持っていって、避難されているお母さん方に、おにぎりを作ってもらうのをお願いして、皆さんにお配りしました。
だんだんと、おかず類も来るようになったので、比較的、大谷の避難所では、温かいものが皆さんに振る舞われたんじゃないかなと思います。
聞き手
調理はどこでされていたんですか。
川端さん
学校の家庭室を使いました。最初は、作ったものを、厨房にあった配食カートを押しながら体育館に持っていって、卓球台の上に並べて、皆さんに配っていました。
聞き手
避難所にいた方の年齢層はどうでしたか。
川端さん
正月で若い方もいて、幅広い年齢層の方がいました。私も、大体は、地域の方の顔と名前が一致しますけれども、お孫さんやお嫁さんなど、若い方で分からない方も結構おられました。
聞き手
お正月で帰省していた方たちが帰っていって、高齢者の方が残るという形だったのですか。
川端さん
そうですね。
聞き手
小学校が指定避難所になっていると、教育もしなきゃいけないし、避難所もしなきゃいけないということで、難しいこともあったと思いますが、どんな対応をされたか教えてください。
川端さん
まず、学校長は、4日に保護者とメールがつながり、状況を把握して、5日に徒歩で学校に来られました。そのとき、私もお話して、事後報告で申し訳ないですけれども、こういう形で学校を使わせてもらっていますと言ったら、全部お任せするので好きなように使ってくださいということでした。職員室は管理すべきものが多々あるので、立ち入らないでほしいと言われましたが、あとはどの部屋を使ってもよいので、お任せしますという形で、ありがたかったです。
実際に授業というか学習会を開始したのが1月11日です。
聞き手
動線を生徒と避難者で分けるような工夫など、何かされていましたか。
川端さん
生徒の皆さんも被災者なので、通常時は同じところにいて、当時は、校長室で勉強会をすると声掛けしておられた。学習会が終わったら、また体育館や避難所で避難所生活という形が続きました。そのときは、23名の生徒中、親戚のうちへ行っていた方や、当日、ここにいない方もいましたので、10名前後だったかな。
あとは、子供たちが肩揉みボランティアをしますということで、避難所へ来て、皆さん揉んでもらったりしていましたね。
聞き手
避難所運営と学校運営の両立が、学習の機会を奪うことになっているという考え方もありますが、どうでしょうか。
川端さん
私も、子供が3人、この学校にお世話になっている立場として、多少はあると思いますけど、私を含めて、大谷地区の人は、皆さん、何というか、地域性もあって、それは仕方ないよねという思いで、我慢したりする方が多々おられます。
先日も、ボランティアの方から、もっと怒ったほうがいいですよと言われたんですけど、そんな怒ることないな、仕方ないねって。だって、役所には役所の仕事があって、マンパワーも足りない中でやっているのも分かっていますし、例えば、自衛隊の対応が遅かったんじゃないかとか、マスコミの方も含めて、お話しされますけど、そんなことはないですよ。自衛隊の方も二日の晩だったかには、入ってきていますし、感謝こそすれ、批判することは全くありません。頼れるところはこうやって頼りながら、お互いを尊重し合うことが大事なので、あまり批判一辺倒というのもどうかなという思いは持っています。
だから、私たちも、学校から言われることは尊重していますし、お互いさまでやっていけば比較的うまくいくんじゃないかな。私がこの避難所を今も運営していますけれども、長期的な避難で一番の問題点は、やっぱりストレスなんです。居心地が悪いようになったら、皆さん、去られるわけで、長期的に過ごすときには、いかに皆さんが居心地よく毎日を過ごせるかというのが、自分では、一番大事に思ってやっているところですね。
聞き手
ルールを決めたりもしていたのでしょうか。
川端さん
発災二日目の朝には、皆さんが体育館の中にいて、メガホンを持って、ステージに上がって、亡くなられた人の情報も入ってきていましたので、皆さんは生かされたんだ、みんなで、ここで踏ん張って生きていこう、ただ、みんなで過ごすにはルールが必要だから、これから皆さんで協力しながらルールを守っていきましょうということはお伝えさせてもらいました。
避難所とはいえ、学校の建物を借りているんだから、返すときにはきれいに返せるように、ということでルール作りをして、それに沿ってくださいということで、ルールができたときに、ステージに上がることも何回かありました。
聞き手
避難されている人は大体、体育館をメインで使っていたのですか。
川端さん
体育館も使いましたし、1階の部屋をペット部屋にしました。意外と、後から気づいたんですけど、ペットは家族と同じような形で生活される方もたくさんいましたので、猫や犬を連れてこられた方に入ってもらうペット部屋を確保しています。3階は高齢者の方が使っていました。2階は隔離部屋という形です。残りは体育館の中と、体育館に中二階があって、これが非常に使い勝手がよくて、今でも、一時的に来られた方には、そちらを使っていただいています。
聞き手
部屋の中での人の分け方は、男女別や家族ごとでされていたのでしょうか。
川端さん
最初は地区ごとですね。大体、地域で顔見知りの方とか、親戚の方が集まっていました。こちらから指示したわけじゃなくて、自然と、そういう形で皆さん分かれていました。
聞き手
部屋の使い分けは、変わることもありましたか。
川端さん
1階はペット部屋でしたが、そこも隔離部屋にしたり、高齢者が3階は辛いとなってきて、時間が経って津波も心配なくなってきたし、看護師さんが見て回るのにも都合がいいということで、足の悪い方や高齢者の方、要介護者の方を1階に移したり、途中から、部屋の移動は何回もしましたね。その都後、掃除したり、運んたりしました。千葉県の派遣職員の方も3月まで来ていただいてましたし、看護の方は、山梨の県立大の方が最初の1週間来られて、その後は、日本災害看護学会の皆さんに来ていただきました。
あと助かったのは、皆さんも被災者なんですけど、勝手連的に、ボランティアで協力していこう、自分も何かできることがあるんじゃないかという方もおられて、二日の日には、もう皆さん協力してくれていました。
一番難しいのはトイレで、水が来ないので、水洗トイレは使えないし、そのままにしておくと、衛生上もよくないので、最初はビニールを2枚がけして、便を出して、要らない紙を、その上に乗せて、次の方にしていただくようにしていました。凝固剤も使いました。そういうトイレを掃除する班とか、館内の清掃班、それから、弁当や炊き出しを配食する班と、物資が来るようになってからは、物資の管理の班、多いときで4班に分かれて、40、50人、炊き出しをされたお母さん方も入れれば全部で60人ほど、皆さん、自主的に参加したいということで、お手伝いをしてくださいました。
聞き手
電気は、どうしていたんですか。
川端さん
発電機がありました。分団には1台、常設されていますし、大谷地区は、この珠洲市の10地区内で唯一、消防の分署があるので、そこの発電機ですとか、地域の発電機もありました。町内で、キリコ祭りをする際の明かり取りとして発電機を備蓄されている地区がいくつかあるので、そういった発電機を持ち寄っていました。
聞き手
電気に関しては、そんなに苦労しなかったということですか。
川端さん
極力、発電機は外に出していたんですが、日中はいいとしても、夜はやっぱり、発電機をかけっ放しだとうるさいので、ずっと動いているわけではなかったですね。燃料も必要ですし、ガソリンとかそういったものは、自衛隊の皆さんに運んでいただきました。
聞き手
情報収集はどうされていましたか。
川端さん
消防団で水や食料を各地域に運んでもらうときに、安否確認も、具合が悪い方がいないかとか、人が何名おられるとか、通常時は電話で済むことなんですけど、電話が使えないので、情報収集を兼ねて、足を使って、物品を配布していました。
聞き手
車椅子の方、要介護の方とか、避難所に来たかったけど、たどりつくことができなかったという方はいらっしゃったんですか。
川端さん
最初のうちは、多分、来ていない方もいたと思います。道路状況が見えて、安否確認に行けるようになって、区長さんや消防団員を通して、そういう方がいるということが分かったら、地域の方に送ってもらったり、消防団が連れて来たりして、徐々に増えてきました。
聞き手
自分で避難所へ行けない方は大谷小中学校で過ごしていただいたという感じだったのですか。
川端さん
大谷地区の中で、馬緤と大谷が交通の面で分断されていましたので、高屋までは馬緤の皆さんにお願いして、私たち大谷では、ちょっと遠いんですけど、真浦までを管理するという形で、名簿作りというか、どういう方がおられるかを全部把握しながら動いていきました。
聞き手
名簿は、用意はなくて、一から作られたんですね。
川端さん
最初はパソコンも何もなくて手書きでした。たまたま被災した中に市職員もいて、名簿作りと、行政側との連絡をお任せしました。ほかに、看護師3名、介護士1名もおられて、看護師はけがをした方の対応、介護士は高齢の方の様子を見ていただきました。
聞き手
大谷小中も指定避難所なので、マニュアルなどもあったかと思うんですが、これはよかったとか、全然使えなかったということはありますか。
川端さん
恥ずかしい話ですが、私は、マニュアルを全く見ていませんでしたね。珠洲市は大きく10地区に分かれており、当時、自主防災組織が完全に出来あがって、報告書も上げていたのが3地区ぐらいしかなかったと思います。大谷も、区長さんが中心となりながら、大体、出来あがっていて、防災訓練でも、そういう方々が安否確認をして、公民館に知らせて、そこから行政に、トータルの数を上げたりもしていたんですが、今回は何せ通信が使えませんでしたし、区長さんも正月で金沢に行っていた方もいて、全員が大谷地区にいたわけでもないしで、安否確認さえもできない状況でした。
聞き手
さきほどの名簿のように、こういうものを事前に作っておけばよかったなということはありますか。
川端さん
確かに名簿があれば、あとはチェックをつけるだけで済むので楽かもしれません。ただし、今回は正月で、通常の住民でない方も結構いましたので、それはどうしても手書きでするしかないですね。記載の順序づけなど細かいところは、職員の方にお任せしていたので、苦労されたと思います。
聞き手
職員さんが通常勤務のような感じでやってくれたと。避難所としては、運営のマニュアルはなかったということですね。
川端さん
自主防災組織を立ち上げた地区では作っているという話も聞いていたんですが、他の地区は、昔のものはありましたけども、中を見ると、同じ人がいろんなところに出てきて、全く機能しないということで見直しをかけていた途中だったので、まだ仕上がっていなかったんじゃないかと思います。
そういった中でも、区長会長さんが中心となって、通信が取れるようになってからは、区長さんのグループLINEを作って色々発信されておられるので、今は大分違うと思います。
私たちが知りえた情報、行政からの連絡、配食の案内もそうですけども、区長会長さんにお願いして、情報をLINEで各区長さんにお知らせしてもらって、各区長さんから、その地域の在宅の方にもお知らせしてもらうという形で、皆さんに周知されるようなシステムになっています。
聞き手
外部との通信も最初は取れなかったということですが、いつぐらいから取れるようになったんですか。
川端さん
まず、6日に、KDDIがつながるようになりました。たまたま私もKDDIだったので、本部を運営するのに自分の番号を伝えたら、至るところから電話がかかってきましたね。
次はソフトバンク、ドコモの順でした。その後、電気が来たのが16日で、これは、避難所に直接電源車を接続して、その中だけ通電されていました。18日にはスターリンクが使用可能になって、Wi-Fi環境を皆さんが使えるようになりました。
聞き手
川端さんご自身は、どちらに避難されていたのでしょうか。
川端さん
家族は2次避難で立山に連れて行きました。私は、翌日1人で避難所へ帰ってきています。
聞き手
それからは避難所で生活されていたんですか。
川端さん
そうですね。途中からはうちへ帰って寝ていました。
聞き手
正月明けから、働いている方は、日中は仕事場に行って、避難所は夜に寝るだけということもあったかと思いますが、こちらもそうですか。
川端さん
豪雨もありましたし、仕事をされている方で、自宅に住めない方は、いまもそうですね。
聞き手
今、避難所の隣に仮設住宅を建てていますが、大谷の避難所を閉じるのは延期になったんですか。
川端さん
延期になりました。本来なら、10月中頃には、仮設住宅に皆さん入っていただける予定だったんですが、豪雨があったので入れなくなりました。
聞き手
今のところ、仮設住宅に皆さんが入って避難所を閉じられそうな時期の目安はいつ頃ですか。
川端さん
早くて12月末ですかね。建物はもう出来上がっているんですが、浄化槽に泥が入ったということで、外して、また入れ直しなんですが、元と同じ200人槽だと、発注してから来るまでに3か月かかって、年越しが確定になるので、今は50人槽を4つ発注して、それが来たら入れ替えるという形で、うまくいけば年内には入れると説明を受けています。
聞き手
避難所として使う上で、学校にこれがあったらもっと快適だったというものはありますか。
川端さん
お風呂ですね。今は、おかげさまで自衛隊のお風呂が公民館前に設置されて、大変助かっていますが、当初から、お風呂があればいいなと思います。私も、1月20日に家族と2次避難所に行くまで、お風呂に入っていませんでしたし。
聞き手
学校にはシャワーもなかったんですね。
川端さん
ないです。ポータブルシャワーを設置したのが1月27日です。
豪雨について
聞き手
地震を踏まえて豪雨の時は対応が可能になったことはありますか。
川端さん
道路が通行不可能になったのは豪雨も一緒なんですが、スターリンクも発災3日目には1台来ていますし、対応は早くなっています。通電に関してもそうです。
あとは、私たちの地域は、テレビ放送が全部有線で、ケーブルが使えないためにテレビが見られない、生の情報が聞けない。どの地区に行っても、皆さんから、テレビをつけてくれ、テレビを見られないのかと、よく言われました。
聞き手
豪雨のときは、トイレはどうでしたか。
川端さん
トイレもまたやり直しでしたけれども、私たちも、培ったノウハウがあったので、比較的、早く対応できたかなと思います。
聞き手
避難所は、1回閉めたものを、豪雨でもう一回開けたのではなくて、ずっと開いていたのですか。
川端さん
仮設住宅が10月中旬頃に出来上がるという話がありましたので、私たちも閉鎖に向かって準備はしていたんです。色々片づけたりしていたものをまた設置してということになりました。水が来ていれば、もっと楽だったんですが。
聞き手
豪雨のときは、どのぐらいの人が大谷小中に避難されたんですか。
川端さん
初日はですね、事業者の方もいて、92名だったかな。次の日の夕方5時ぐらいに、大谷峠を取りあえず通れるようにしていただいて、それから事業者の方は一斉に出ていったので、40名ぐらいまで減りましたね。徐々に自宅へ戻ったり、こちらから出ていって、今日現在で、豪雨と震災、両方合わせた避難者数は26名になっています。
聞き手
大谷小中の避難所では、仕切りがあまりないですが、普通に皆さんの意向ですか。
川端さん
そうです。震災の際も、豪雨の際も、希望があれば、仕切りをおつけしますよと皆さんに周知はしているんですけど、このままのほうがいいということでした。今回の場合は、テントを希望された方が1世帯いて、1基だけ入りました。
聞き手
避難所を回っていると、1家族1つテントがあったり、仕切りがあったりするので、結構珍しいですね。
川端さん
顔が見えるので、こちらとしても安心というか、具合悪いことはないですか、せき込んでいるけど大丈夫ですかとか話もできていいんです。1.5次避難所のスポーツセンターなんかテントだらけで、ちょっと寂しい感じがするというか、会話もないんじゃないですかね。
聞き手
指定避難所だといろんな人が来るから、仕切りがほしいけど、大谷は、皆さん顔見知りだから、ないほうが安心するみたいなことなんですね。
ただ、どこにも集団行動が苦手な人もいると思うんですが、大谷は大丈夫ですか。
川端さん
全くないということはないです。うちに帰った方もいて、様子を見に行ったりしています。
聞き手
見守りは、消防団の方がされているんですか。
川端さん
消防団もなかなかマンパワーがない状態なんですけど、私たちでたまに行ったり、区長さんにお願いしたり、近所の方からお話を聞いたりしています。遠くにいるお子さんには、避難所から自宅に帰ったよということで連絡はしてあります。
被災経験を振り返って
聞き手
避難生活を経験されて、事前にしておけばよかったことはありますか。
川端さん
やっぱり一番はトイレの問題。たまってきたら衛生上もよくないですし、ぜひ、自治体単位で1基ずつ、移動トイレみたいなものを持っていただきたいなと思います。今回の地震のような能登全体の災害だと、手配しても、全然、個数が足りないということになるでしょうけど、豪雨のような局地的な災害の場合ですと、石川県内の市町から、そういったものが入ってくれば、それだけでも全然違ってくると思います。やはりトイレは我慢のしようのないものですから、そういったものが、あってもいいんじゃないかなと。ぜひ予算づけして、確保していただきたいです。
これは区長会長さんも言っておられるんですけど、私も今回、通信の大切さ、通信ができないことがこんなに不便なのかと感じました。私は元気だよとか、皆さんのお父さん、お母さんも元気だよっていうことを伝えたいけど伝えられないことがもどかしかったですね。スターリンクなども、常備というわけにはいかないでしょうけども、指定避難所にはそういったものがすぐ設置できるようにしておかないと都合が悪いと思います。
今回の地震で、大谷の人は孤立していると言われるんですが、私たちは農道を通しながら、何とか脱出させていましたので、孤立と言われていることも知りませんし、最初の頃は、自衛隊にしろ、消防にしろ、警察にしろ、安否確認に来られた方がたくさんいました。電話1本で安否確認できるのに、それができないことで、いかに情報が錯綜していたか。今回の豪雨でも、仁江地区とかを消防団が徒歩で回ってくる状況になったので、安心した通信確保ができればと思います。

伝える
- 体験を語る
-
避難所・避難生活
-
七尾市矢田郷地区まちづくり協議会 防災部会元会長、石川県防災活動アドバイザー、防災士
佐野藤博さん
「これまで培った防災の知識を生かして、規律ある避難所運営につなげた」 -
(輪島市)澤田建具店
澤田英樹さん
「現場からの提言――避難所を「暮らしの場」に」 -
輪島市上山町区長
住吉一好さん
「孤立集落からの救助とヘリコプターによる集落住民の広域避難」 -
珠洲市蛸島公民館長 田中悦郎さん
「厳しい環境の自主避難所を皆さんの協力のおかげでスムーズに運営」 -
珠洲市正院避難所協力者 瓶子睦子さん、瀬戸裕喜子さん
「皆で力を合わせ、助け合って避難所を運営」 -
珠洲市宝立町区長 佐小田淳一さん
「高齢者も多い学校の避難所で感染症対応を実施」 -
珠洲市大谷分団長 川端孝さん
「通信の重要性を痛感しつつも、多くの方の協力のもとで避難所を運営」 -
珠洲市日置区長会長 糸矢敏夫さん
「難しい判断も迫られた避難生活を経て、地区のコミュニティ維持に努める」 -
珠洲市蛸島区長会長 梧 光洋さん 蛸島公民館館長 田中 悦郎さん
「想定にない大人数の避難に苦労した避難所運営」 -
珠洲市飯田区長会長 泉谷信七さん
「学校の運営にも配慮しながら、多くの方がいる避難所を運営」 -
珠洲市上戸町区長会長 中川政幸さん
「避難生活を通じて、防災の重要性を再認識」 -
珠洲市若山区長会長 北風八紘さん
「防災訓練の経験が避難所運営に生きた」 -
珠洲市直区長会長 樋爪一成さん
「想定と異なる場所で苦労しながらの避難所運営」 -
珠洲市正院区長会長 濱木満喜さん 副会長 小町康夫さん
「避難者・スタッフ・支援者の力を結集して避難所を運営」 -
珠洲市三崎区長会長 辻 一さん
「普段の防災活動が災害時の避難に生きた」 -
珠洲市大谷地区区長会長 丸山忠次さん
「防災士の知識も生かし、多くの方と協力しながらの避難所運営」 -
珠洲市大谷地区 避難所
坂秀幸さん
「孤立集落における自主避難所の運営に携わって」 -
珠洲市上戸区長
今井 真美子さん
「全国からの支援に支えられ、
防災士として避難生活をサポート」 -
珠洲市宝立町区長会長
多田進郎さん
「避難所の運営にあたって」 -
能登町立高倉公民館長
田中隆さん
「避難所運営を経て、地域のつながりの大事さを再認識」 -
能登町防災士会会長
寺口美枝子さん
「防災士の知識が災害時に生きたと同時に、備えの必要性を改めて感じた」
-
七尾市矢田郷地区まちづくり協議会 防災部会元会長、石川県防災活動アドバイザー、防災士
-
行政
-
輪島市復興推進課(当時)
浅野智哉さん
「避難所運営・広域避難・交通復旧の実態と教訓」 -
輪島市上下水道局長(当時)
登岸浩さん
「被災後の上下水道の復旧とその体験からの教訓」 -
輪島市生涯学習課
保下徹さん
「災害対応・避難所運営の課題と連携」 -
輪島市環境対策課
外忠保さん
「災害時の環境衛生対応で感じた多様性への課題」 -
輪島市防災対策課長(当時)
黒田浩二さん
「防災対策課として、刻々と変化する状況への対応と調整に奔走」 -
輪島市防災対策課
中本健太さん
「災害対応と避難所運営の課題」 -
輪島市防災対策課(当時)
新甫裕也さん
「孤立集落対応の実態と教訓」 -
輪島市文化課長(当時)
刀祢有司さん
「文化会館での物資受け入れ業務と、文化事業の今後の展望について」 -
輪島市土木課長(当時)
延命公丈さん
「技術者としての責任を胸に、被災直後から復旧に奔走」
-
輪島市復興推進課(当時)
-
消防
-
七尾消防署 署長補佐
宮下伸一さん
「道路の損壊をはじめ、過酷な状況で困難を極めた救助活動」 -
七尾消防署 署長補佐
酒井晋二郎さん
「不安や課題に直面しながらも、消防職員として全力で責任を果たした」 -
輪島消防署(当時)
竹原拓馬さん
「消火活動・救助活動の経験から職員一人ひとりの技術向上を目指す」 -
珠洲消防署 大谷分署 宮元貴司さん
「拠点が使えない中、避難所の運営にも協力しながら活動を実施」 -
珠洲市日置分団長 金瀬戸剛さん
「連絡を取り合えない中で、それぞれができる活動をした」 -
珠洲市三崎分団長 青坂一夫さん
「地区が孤立し、連絡も取りづらい中で消防団活動に苦心」 -
珠洲市消防団鵜飼分団長 高重幸さん
「道路の寸断など厳しい環境の中、救助活動に尽力」 - 珠洲消防署 中野透さん、源剛ーさん 「殺到する救助要請への対応と緊急援助隊の存在」
-
珠洲市若山消防団長
森定良介さん
「救助活動や避難所運営での苦労や課題、
災害への備えの重要性を再認識」
-
七尾消防署 署長補佐
-
警察
-
医療機関
-
(七尾市)公立能登総合病院 診療部長
山端潤也さん
「令和6年能登半島地震の経験 ~過去の災害に学び 活かし 伝え 遺す~」 -
輪島病院事務部長(当時)
河崎国幸さん
「災害対応と病院の今後の地震対応にかかるBCP」 -
珠洲市健康増進センター所長
三上豊子さん
「支援団体と協力し、全世帯の状況把握や、
生活支援を実施して」 -
珠洲市総合病院
内科医長・出島彰宏さん、副総看護師長・舟木優子さん、薬剤師・中野貴義さん
「2人で立ち上げた災害対策本部と過酷な業務」 -
志賀町立富来病院 看護師・川村悠子さん、事務長・笠原雅徳さん
「物資だけでは解決しない~災害時のトイレに必要な「マンパワー」と「経験」~」 -
(能登町)小木クリニック院長
瀬島照弘さん
「能登半島地震における医療対応と教訓」 -
(能登町)升谷医院 院長
升谷一宏さん
「過酷な環境下で診療にあたり、多くの方の健康を支えた」
-
(七尾市)公立能登総合病院 診療部長
-
教育・学校
-
七尾市立天神山小学校長(当時)
種谷多聞さん
「今こそ、真の生きる力の育成を!~能登半島地震から 学校がすべきこと~」 -
珠洲市飯田高校2年生
畠田煌心さん
「ビニールハウスでの避難生活、
制限された学校生活、そんな被災体験を未来へ」 -
珠洲市宝立小中学校5年生
米沢美紀さん
「避難所生活を体験して」 -
珠洲市立緑丘中学校3年生
出村莉瑚さん
「避難所の運営を手伝って」 -
志賀小学校 校長・前田倍成さん、教頭・中越眞澄さん、教諭(当時)・岡山佳代さん、教諭・野村理恵さん、教諭・側垣宣生さん、町講師(当時)・毛利佳寿美さん
「みなし避難所となった志賀小学校」 -
能登町立柳田小学校長
坂口浩二さん
「日頃からの地域のつながりが、避難所運営の土台に」
-
七尾市立天神山小学校長(当時)
-
企業・団体
-
ボランティア
-
関係機関が作成した体験記録

