体験を語る
- 企業・団体
被災したスーパーの営業再開で地域の皆さんの生活の助けに
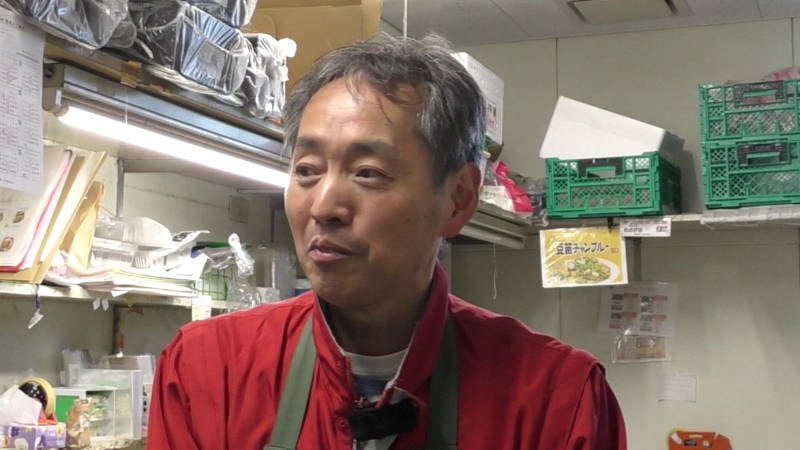
| 場所 | 珠洲市 |
|---|---|
| 聞き取り日 | 令和6年9月19日 |
地震発生当初
聞き手
当時の被害状況について教えてください。
大丸さん
私は年中無休のスーパーの経営側で、1月1日しかお休みがないので、ここぞとばかりにお酒を飲んでいました。
友達と一緒に還暦の役を受けに8時過ぎに神社へ行って、それから、お正月だということで飲んだり食べたりして、疲れて寝たんです。午後3時半頃に起きて、ろくに食べていなかったので、何か食べようと思って、流しのほうに行ったら、ものすごい揺れがありました。それまでも地震がよくあったので、初めはすぐ終わるものだと思っていたんですが、今回の揺れ方はひどいなと。うちの中が全部ひっくり返って、これはやばいということで、消防団員は、本当はこういう大地震があり、大津波警報が出ると、分団の車庫に行き、消防のポンプ車を動かし、町民の皆さんに高台に避難するように案内して回らなきゃいけないんです。本当に、あの地震に遭った人しか分からないと思いますが、何回も訓練はしてきたけれども、まずうちの中がひど過ぎて、それどころじゃない。
店でも毎年、震度7を想定した避難訓練をやるんですよ。もう何回もやっていて、従業員にも、あなたは地震が起きたらどうするのかということを毎年、紙に書いて、更新してもらっているんです。ただ、結局、何のために書いたのかと思うぐらい、書いたことはできない。あの地震は、本当に受けてみてくださいと言いたいぐらいに、本当に何もできないです。
うちを片づけているときに、大津波警報だから高台に避難しろという消防の連絡も入ってきたんですけど、とにかく、うちの状況がひどくて、今も傾いたまま住んでいます。
私のうちは近くの飯田高等学校が避難所で、娘に高台に避難しなきゃいけないと言われて避難しました。1歳ぐらいの子供もいたので、とにかくその子優先で、1月1日で、もちろん寒いですから、毛布でも何でもありとあらゆるものを持って行きました。
避難所へ行くと、結構、人が集まっていて、1月1日の5時過ぎにはもう暗くなって、停電になっているのも気がつかず、体育館に行くのにしても、暗くて道がよく分からなくて、足元も悪い中で行ったのをよく覚えています。中に入っても寒かったですね。
ちょっと落ち着いたのが2日のお昼ぐらいかな。何も食べてないし、かといって、不思議と全然おなかはすいていないんですね。ある程度落ち着いたら、私も消防団員だから、様子を見て回ろうかなと思ったんですけども、マンホールが浮いていたりして、道がものすごくひどくて、車を動かすのもままならない。
聞き手
避難についてはどのような感じでしたか。
大丸さん
町内でも、区長さんが来て、どこのうちに何人いて、足元悪い方が何人、小さい子が何人というのは知っているはずだけど、みんな避難するところがばらばらでした。今回は特に正月で、向こうの神社に行っていたとか、買い物していたとか、車に乗っていたとかで、一番近いところに避難する感じでした。
私は、後期高齢者の母親と、娘と1歳の赤ちゃんと一緒に、最初は、学校の教室の中に避難しました。その教室は30人ぐらい雑魚寝というか、体育座りや、机に寝ていました。体育館で寝ている方もいましたけど、寒いですし、教室は一応エアコンもついたのでよかった。
教室は床が冷たくて、体育館の2階に柔道の畳があったので、これを下ろそうとなって、初めは男2人ぐらいで運んでいたのかな。途中でやってられないと思って、助けをお願いして、どんどん教室に畳を運んで、かなり汗も出たので、風邪を引かなくてよかったですが、あれで結構それなりになったかなと思います。
でも、みんな食べ物がなくて、パンなどを1人1個でお願いしますと配っていて、これで今晩終わるのかとなったのを覚えています。我々は我慢できるけど、特に小さい子なんか、かわいそうだな、何か分けてあげたいなと思って、店に行ったら何かあるかもしれんなと思って、店からおせちの残りみたいなものを持ってきて、みんなに配る分はないので、教室の中で、食べてくださいと配って、そのときもものすごく助かったという声がありました。そういうのもあったので、早く店を開けたいなと思ったんですね。
その後は、やっぱり赤ちゃんがいると、どうしても泣くので周りの人に申し訳なくて、私だけならずっと避難所にいたかもしれないけど、早くうちに避難できればいいな、電気が来たら、すぐにうちを片づけて、みんなで避難しようと言っていました。そう言っていると、4日だったかに電気が来て、一目散にうちに行って、家の中も全然片づいてなくて、ぐちゃぐちゃなんだけど、取りあえず住めるような部屋を2部屋だけきれいにして、小さい子とおばあちゃんが寝る部屋を確保しました。避難所から出ていくときに、大丸さん、うちに帰れるんですか、いいなとみんなに言われて、やっぱり、みんなここにいたくないんだろうなと思いました。
聞き手
1日は、1つの教室に30,40人いたんですか。
大丸さん
全部が埋まっているわけじゃなくて、上へ行くにつれ減っていました。飯田高校は、耐震設備はあるけども、1日の後も大きい地震が何回かあって、そのたびにみんな怖くて震えている状況だから、上に行きたくない、行っても2階まで、できれば1階にいたいという感じに避難していたのを覚えていますね。
聞き手
体育館にも人がいっぱいいたのですか。
大丸さん
体育館は寒いのでそこまでではなかったです。幾ら大きな暖房を出しても寒いなと思っていました。
聞き手
当時エアコンがついたということは、飯田高校には電気が通っていたということですか。
大丸さん
あったんだと思います。ただ、途中で何時消灯にするとか制限があって、私もよく分かってないんですけど、予備電源だったのか、つけっ放しというわけではなかったような気がします。
聞き手
水はどうでしたか。
大丸さん
正院の体育館とか、いろいろなところに防災の備蓄が置いてあったんです。飯田高校の前の坂道を通ってそれを運びました。飯田高校に車で来た人がみんな坂道で車を止めるもんだから、荷物も上げられない状態でした。地割れがひどくて、車もちょっと動かしたら危ないような道でした。あまり行ってないのでよく分からないですけど、学生がもう登校しているから、今はよくなっているのかな。
聞き手
教室には、高齢者の方や子供がいらっしゃる方を優先的に入れていたのですか。
大丸さん
本当はそうすべきだったと思うんですけど、早いもの勝ちみたいな感じになっていました。私も初めは体育館にいて、どうも教室のほうはエアコンもついているみたいだという話を聞いたので移動しました。教室へ行くまでも、道が結構割れていて危なかったのですが、意外と行けました。
聞き手
避難所では、高齢の方や子供がいづらいというお話も聞くのですが、そんな感じはありましたか。
大丸さん
気兼ねするところはあると思います。
聞き手
避難所を取り仕切る方はいたのでしょうか。
大丸さん
私はずっと避難していたわけじゃないので、避難所に関して、その後どうなっていたのか、分からない部分があります。うちへ帰ってからは、私はずっと店に来て、荷物を配ったりしていたので、高校には行っていません。
聞き手
トイレはどうされていたのでしょうか。
大丸さん
男性は外に行ったりすればいいですけど、女性は水を流せないので、どうしていたのか。ほとんど学校の中で簡易トイレを使っていたんじゃないかなと思います。
聞き手
通信の状況はどうでしたか。
大丸さん
飯田高校ならではですけど、生徒1人にタブレットが渡されていて、教室に置いてあるんですね。誰が許可したのか、タブレットを見ている人がいて、使ったら元に戻してくださいという感じで、割とインターネットで情報が得られました。
ほかのところは多分そんなことはできていないと思うんですよ。ほかのところは、ずっと停電だったとか、発電機を使ってかろうじてやっていたとか、ろうそくを立てていたと聞きました。だから、私の行った飯田高校は十分恵まれていた避難所だったんだろうと思っています。途中から、もっといい避難所もあるという情報も流れていましたけど、その辺は、よく分からないです。
聞き手
火災はあったのでしょうか。
大丸さん
私のエリアではなかったんですが、隣の宝立町で火災があったと聞いております。そのエリアは津波の被害がかなりひどく、地震の家の倒れ方もここよりひどいということで、私の住んでいるエリアはまだいい方だったと後々分かりました。病院も近いし、3、4日にはもう電気が来て、私のスーパーは営業できなかったけど、ゲンキーというドラッグストアが開いていたおかげで、かなり助かったと思います。
私も2日から店の営業をやろうとして、店の中に結構な材料をストックしていました。ただ、営業ができなくて、スーパーマーケットの商品は賞味期限が短いものばかりなので、うちの社長をはじめ、これは困っている人たちに配ろう、警察、消防など尽力していただいている方は絶対大変だし、飲み物、食べ物もないだろうということでかなり配りました。
もちろん無償です。持っていてもどうせ捨てるか腐らせるだけだろうということで、後々ものすごく喜ばれましたけれども、そのときできることということでそれを配りました。
スーパーの営業再開
大丸さん
この店も今はこうやって平気で営業していますけど、そのときは何としてでも店を開けて、珠洲市の方に少しでも食糧を供給したいという思いがあったので、1月11日に左の入り口方だけ開けて営業を始めました。
もちろん仕入れは思うようにいかなかったですし、大変なことばかりでしたね。9時にオープンして昼の3時に閉店ということで、それぐらいじゃないと、人手が全然いなくて、前は大体60人弱働いていたんですけども、今は30人もいない。
聞き手
もともとは何時から何時でやっていたんですか。
大丸さん
9時オープンの夜8時閉店でやっていました。お客さんから、本当に開けてくれてありがとうと何度もお礼を言われましたし、私は経営側ですから、どんどんやりたいと思います。でも、働きに来てくれる方は、本当にうちのこととか、いろいろやることもいっぱいあるだろう中で、幾ら仕事とはいえ、店のことをやってくれていることに本当に感謝しています。
もちろん、いなくなった従業員さんも、決して嫌で辞めたわけではなく、うちもなくなり、仕事もほとんどできない状態で、食事もままならない、もうこんな生活が嫌だという感じで、金沢のほうに行かれた方や、年配の人は息子さんや娘さんのうちへ行く方もいて、半分ぐらいになったということです。
10か月たって、ここまで何とか店を開けられるようになったけど、今でも青果の人間がいなくて、自分が昔やったことがあったから、記憶をたどりながら仕事をやっています。うちは、魚の部門とお惣菜の部門が売りのお店で、そのスタッフが割といたので、結構うまくやれたと思います。その代わり肉を切る人が誰もいなくなり、出す人もいなくなりました。見てのとおり、肉は並んでいますけども、実は、我々の入っている信州グループの援助もあり、あとはJAの肉のパッケージセンターのところに頼んで、今は誰も肉を切る人がいなくても、肉を並べることができて、営業ができているということになります。
レジも今4台しかありません。本当は7台ぐらいあったんだけど、それも潰して今のレジ体制になっています。あそこにかけ時計があるんですけど、いつも4時10分だねとよく言われます。いつもあれを見て、その頃のことを思い出して頑張ろうということで電池を入れていないのですが、この時間に地震があったんだよということを知らせるような時計にもなっています。
もう一つの出入口の方が本当は人が多く出入りするんですけども、坂道が結構やられて、セキュリティーのこともあるのでずっと閉鎖して、今は出入口1つだけでやっています。
トイレは今もまだ、お客さんも我々も使えない状態です。簡易トイレを使っています。男性はともかく女性は大変だろうなといつも思っています。隣の倉庫のトイレは使えるようになったんですが、ここは何で使えないのか。トイレに関しては、本当にお客様には大変御迷惑をおかけしています。

聞き手
発災当時の消防団の活動は、どんな形で行われたんですか。
大丸さん
後で聞いたところ、1人、ふだんの訓練どおりのことをやろうという方がいて、車に乗って、ポンプ車を取りに行きました。本当は、津波警報があったから、後々のことを思うと車で行っちゃいけなかったのかもしれませんが、車を分団の車庫に置いて、ポンプ車を出して、大津波警報が出たから高台に避難するようにと案内して回ったそうです。その後、津波が来て、彼の車は新車だったんですけど、流されてしまいました。
まず津波で犠牲者がいなくてよかったなということと、あと、うちがやられた人たちは本当にかわいそうだな、何とかしてあげたくても、全然何もできないなということがあります。従業員にも、うちがやられて駄目になった人がいます。この前の大雨の川の氾濫でも1人、新しいうちだったのに、川が氾濫して、津波よりひどいと私に非常にショックを受けた顔で報告していました。
大雨は事前に分かりますから、避難もできますけど、地震は、ある日突然来て、やるべきことはやろうと思ってもできなくて、気がついたら高台に避難しなきゃいけなくなる。うちは近いから、服だとか色々と持っていったけど、軽装で避難している人もいっぱいいましたよ。小さい子供を見つけたら、うちの子供の服を貸してあげたりしましたから、持っていってよかったなと思います。
被災経験を振り返って
聞き手
今の経験を踏まえて、今後のことについてご意見をお聞きできればと。
大丸さん
今回の大雨にしても、1月1日の地震にしても、もちろん未曾有の経験なんですけども、なってみて初めて分かることってすごく多いなと思いました。これだけ地震もあったのに、今に大きいのが来るよと言われていたのに、我々はどれだけ訓練をやっていたんだろう、甘い訓練だったな、でも、これぐらいしか普通やらないよねと安心していたなと、後々思いました。
避難訓練はもちろん大切で、絶対やらなきゃいけない、やるべきだと思います。ただ、例えば火災訓練のときも消火器を使ってやるじゃないですか。あれも、分かっているからとか、やりたくないという人が結構いるんです。何事も経験しないと分からないので、本当に訓練はできるだけ参加していただくことが大事ですね。
あとは、避難所に人がいっぱいになったときに、誰が音頭を取るのかみたいなことを、例えば飯田高校が避難所になったとき、前回の震災のときはこうやってクラスの中に入ったから、次はどうするということを、大まかにでも組み立てて管理しておけばいいのかなと思いました。

伝える
- 体験を語る
-
避難所・避難生活
-
七尾市矢田郷地区まちづくり協議会 防災部会元会長、石川県防災活動アドバイザー、防災士
佐野藤博さん
「これまで培った防災の知識を生かして、規律ある避難所運営につなげた」 -
(輪島市)澤田建具店
澤田英樹さん
「現場からの提言――避難所を「暮らしの場」に」 -
輪島市上山町区長
住吉一好さん
「孤立集落からの救助とヘリコプターによる集落住民の広域避難」 -
珠洲市蛸島公民館長 田中悦郎さん
「厳しい環境の自主避難所を皆さんの協力のおかげでスムーズに運営」 -
珠洲市正院避難所協力者 瓶子睦子さん、瀬戸裕喜子さん
「皆で力を合わせ、助け合って避難所を運営」 -
珠洲市宝立町区長 佐小田淳一さん
「高齢者も多い学校の避難所で感染症対応を実施」 -
珠洲市大谷分団長 川端孝さん
「通信の重要性を痛感しつつも、多くの方の協力のもとで避難所を運営」 -
珠洲市日置区長会長 糸矢敏夫さん
「難しい判断も迫られた避難生活を経て、地区のコミュニティ維持に努める」 -
珠洲市蛸島区長会長 梧 光洋さん 蛸島公民館館長 田中 悦郎さん
「想定にない大人数の避難に苦労した避難所運営」 -
珠洲市飯田区長会長 泉谷信七さん
「学校の運営にも配慮しながら、多くの方がいる避難所を運営」 -
珠洲市上戸町区長会長 中川政幸さん
「避難生活を通じて、防災の重要性を再認識」 -
珠洲市若山区長会長 北風八紘さん
「防災訓練の経験が避難所運営に生きた」 -
珠洲市直区長会長 樋爪一成さん
「想定と異なる場所で苦労しながらの避難所運営」 -
珠洲市正院区長会長 濱木満喜さん 副会長 小町康夫さん
「避難者・スタッフ・支援者の力を結集して避難所を運営」 -
珠洲市三崎区長会長 辻 一さん
「普段の防災活動が災害時の避難に生きた」 -
珠洲市大谷地区区長会長 丸山忠次さん
「防災士の知識も生かし、多くの方と協力しながらの避難所運営」 -
珠洲市大谷地区 避難所
坂秀幸さん
「孤立集落における自主避難所の運営に携わって」 -
珠洲市上戸区長
今井 真美子さん
「全国からの支援に支えられ、
防災士として避難生活をサポート」 -
珠洲市宝立町区長会長
多田進郎さん
「避難所の運営にあたって」 -
能登町立高倉公民館長
田中隆さん
「避難所運営を経て、地域のつながりの大事さを再認識」 -
能登町防災士会会長
寺口美枝子さん
「防災士の知識が災害時に生きたと同時に、備えの必要性を改めて感じた」
-
七尾市矢田郷地区まちづくり協議会 防災部会元会長、石川県防災活動アドバイザー、防災士
-
行政
-
輪島市復興推進課(当時)
浅野智哉さん
「避難所運営・広域避難・交通復旧の実態と教訓」 -
輪島市上下水道局長(当時)
登岸浩さん
「被災後の上下水道の復旧とその体験からの教訓」 -
輪島市生涯学習課
保下徹さん
「災害対応・避難所運営の課題と連携」 -
輪島市環境対策課
外忠保さん
「災害時の環境衛生対応で感じた多様性への課題」 -
輪島市防災対策課長(当時)
黒田浩二さん
「防災対策課として、刻々と変化する状況への対応と調整に奔走」 -
輪島市防災対策課
中本健太さん
「災害対応と避難所運営の課題」 -
輪島市防災対策課(当時)
新甫裕也さん
「孤立集落対応の実態と教訓」 -
輪島市文化課長(当時)
刀祢有司さん
「文化会館での物資受け入れ業務と、文化事業の今後の展望について」 -
輪島市土木課長(当時)
延命公丈さん
「技術者としての責任を胸に、被災直後から復旧に奔走」
-
輪島市復興推進課(当時)
-
消防
-
七尾消防署 署長補佐
宮下伸一さん
「道路の損壊をはじめ、過酷な状況で困難を極めた救助活動」 -
七尾消防署 署長補佐
酒井晋二郎さん
「不安や課題に直面しながらも、消防職員として全力で責任を果たした」 -
輪島消防署(当時)
竹原拓馬さん
「消火活動・救助活動の経験から職員一人ひとりの技術向上を目指す」 -
珠洲消防署 大谷分署 宮元貴司さん
「拠点が使えない中、避難所の運営にも協力しながら活動を実施」 -
珠洲市日置分団長 金瀬戸剛さん
「連絡を取り合えない中で、それぞれができる活動をした」 -
珠洲市三崎分団長 青坂一夫さん
「地区が孤立し、連絡も取りづらい中で消防団活動に苦心」 -
珠洲市消防団鵜飼分団長 高重幸さん
「道路の寸断など厳しい環境の中、救助活動に尽力」 - 珠洲消防署 中野透さん、源剛ーさん 「殺到する救助要請への対応と緊急援助隊の存在」
-
珠洲市若山消防団長
森定良介さん
「救助活動や避難所運営での苦労や課題、
災害への備えの重要性を再認識」
-
七尾消防署 署長補佐
-
警察
-
医療機関
-
(七尾市)公立能登総合病院 診療部長
山端潤也さん
「令和6年能登半島地震の経験 ~過去の災害に学び 活かし 伝え 遺す~」 -
輪島病院事務部長(当時)
河崎国幸さん
「災害対応と病院の今後の地震対応にかかるBCP」 -
珠洲市健康増進センター所長
三上豊子さん
「支援団体と協力し、全世帯の状況把握や、
生活支援を実施して」 -
珠洲市総合病院
内科医長・出島彰宏さん、副総看護師長・舟木優子さん、薬剤師・中野貴義さん
「2人で立ち上げた災害対策本部と過酷な業務」 -
志賀町立富来病院 看護師・川村悠子さん、事務長・笠原雅徳さん
「物資だけでは解決しない~災害時のトイレに必要な「マンパワー」と「経験」~」 -
(能登町)小木クリニック院長
瀬島照弘さん
「能登半島地震における医療対応と教訓」 -
(能登町)升谷医院 院長
升谷一宏さん
「過酷な環境下で診療にあたり、多くの方の健康を支えた」
-
(七尾市)公立能登総合病院 診療部長
-
教育・学校
-
七尾市立天神山小学校長(当時)
種谷多聞さん
「今こそ、真の生きる力の育成を!~能登半島地震から 学校がすべきこと~」 -
珠洲市飯田高校2年生
畠田煌心さん
「ビニールハウスでの避難生活、
制限された学校生活、そんな被災体験を未来へ」 -
珠洲市宝立小中学校5年生
米沢美紀さん
「避難所生活を体験して」 -
珠洲市立緑丘中学校3年生
出村莉瑚さん
「避難所の運営を手伝って」 -
志賀小学校 校長・前田倍成さん、教頭・中越眞澄さん、教諭(当時)・岡山佳代さん、教諭・野村理恵さん、教諭・側垣宣生さん、町講師(当時)・毛利佳寿美さん
「みなし避難所となった志賀小学校」 -
能登町立柳田小学校長
坂口浩二さん
「日頃からの地域のつながりが、避難所運営の土台に」
-
七尾市立天神山小学校長(当時)
-
企業・団体
-
ボランティア
-
関係機関が作成した体験記録

