体験を語る
- 県民

避難所の運営にあたって

| 場所 | 珠洲市 |
|---|---|
| 聞き取り日 | 2024年9月19日 |
| 映像二次利用 | 不可 |
避難所の開設
- 聞き手
-
地震発生当日から避難所が開設されたと思うのですが、開設の状況について教えてください。
- 多田さん
-
私の家が鵜島だったので、実際に宝立小中学校に入ったのは1月2日の早朝でした。地震発生時、私は他の町へ行っていたので、慌てて帰り、鵜島の高台の避難場所へ逃げました。その後、家のことが心配だったので、様子を見に高台に車を置いて家に向かいました。家の様子を見に行ったら家は全壊でした。家に行く途中に家内に会い、だんだん日が暮れていったので、私たちの集落からは一番近い朝日避難所に行きました。朝日避難所は、公の避難所としては指定されていませんでしたが、非常に甚大な地震だったので、公の避難所の宝立小中学校に行くことが出来ませんでした。橋が断裂しており、車も使うことができませんでした。1月1日の晩は呆然とした頭で、みんなと一緒に朝日避難所で過ごしました。余震もずっと続いていましたが、そこにいると安心できました。避難した人は、詰め込みで100人くらいいたかもしれません。寒い中だったので、暖を取るために公民館からストーブや、簡単な布団・毛布を7、8人でリアカーに乗せて持ってきました。朝日避難所の方に向かう途中、宝立小中学校の前にすごい人数の避難者がいたのを見かけました。宝立小中学校の建物は、平成23年にできた最新の耐震構造だったので非常に丈夫で、どんどんそこに人が避難してきました。私は、朝日避難所にみんなと一緒に避難し、一晩過ごしましたが、非常に狭く、たくさん人がおり、横になれるスペースがありませんでした。
一晩明けて、朝日避難所は寝たりすることができないと考え、「宝立小中学校は広いので、お年寄り以外の元気な人は、宝立小中学校へ移動しましょう。」とみんなに呼びかけました。鵜飼大橋は断絶していて、車も通れないので、翌朝、移動できる人だけで、鵜飼大橋からもう一つ川下の方に金峰寺橋を通り、宝立小中学校に向かいました。
 被害の様子を語る多田さん(2024年9月19日撮影)
被害の様子を語る多田さん(2024年9月19日撮影)宝立小中学校に行ったら、お年寄りや区長さんが受付業務をやっていました。バラバラにやっていたので、これではダメだと思いました。宝立町には自主防災組織があり、こうした避難所運営のために作られた組織ではなくて、珠洲市の総合防災訓練にどう参画していくか、事前に計画するための組織でした。当然、避難所の運営なんて全然頭にありませんでした。一体誰がやればいいのかとなり、自分は、書類上、自主防災組織の本部長という名前がついていました。本部長でもあったし、宝立町全体の区長会の会長だったので、自然と自分がやるしかないと思いました。それで、周りにいた区長と一緒に、受付をやっていた人と相談して、自主防災組織の本部長として、避難所運営の中心となる組織を初めてそこで立ち上げました。
- 聞き手
-
1月2日の時点から、自主防災組織が宝立小中学校で避難所の運営を行っていたってことですか。先ほど朝日避難所から移動されたとおっしゃっていましたが。
- 多田さん
-
私が寝泊まりするのは朝日避難所でしたが、避難所を運営するために、宝立小中学校に通っていました。中心にあるのが宝立小中学校で、一番収容人数が多い避難所でした。最初は、1月1日、2日あたりに入ってきた人には、みんな手書きで(氏名を)書いてもらいました。とてもじゃないけれど、紙に書いていては把握が難しく、後で分かったことが、1月1日からここにいたのが800人から900人でした。
そのほか、介護施設・第三長寿園、第一長寿園、柏原の閉鎖した保育所、林業センター、それから助政や鵜島の生活改善センター、保育所に避難している人がいました。道路が断絶して車では行けないので、知り合いの若者のバイクの後ろにのり、「ちょっと回ってくれよ。」とお願いし、「宝立小中学校で、大きい避難所を立ち上げる。」ということを広報しました。そのバイクは途中ではまってしまい、おそらく液状化だったと思いますが、そのバイクを救出するのに、1、2時間かかってしまい「もうやめよう。」となり、バイクはそこに置いてきました。そういった経緯で、宝立小中学校の避難所は正式に開設されました。 - 聞き手
-
地震発生から1週間後ぐらいまでの間、宝立小中学校にほとんどの人が集まっていたということですか。
- 多田さん
-
そうです。ただし、徐々に減っていきました。何故かというと、帰省者がいたからです。この辺が想定外でした。災害ってそういうものですが、1月1日に、こうした大きな災害が起こるとダメなのだと感じました。金沢までの道路が復旧して、金沢まで8~10時間くらいかかりましたが、みんなは仕事もあるし、金沢方面に帰っていきました。それで人数は減っていきましたが、今度は、長寿園を介護施設として開けないといけなくなり、長寿園に避難していた百何十人が宝立小中学校に移ってきて、1月中旬には、300人くらいの方が宝立小中学校にいました。
- 聞き手
-
水や電気はいつ通ったのですか。
- 多田さん
-
水は3日くらいで、陸上自衛隊の給水車が来たので、あまり不自由はしませんでした。電気は4日の夕方、これは関西電力が学校のそばに特別の高圧器というか、発電機みたいなものをつけてくれて、学校全体に電気が行き渡るようにしてくれました。その晩から、エアコンのある部屋は、エアコンが使えるようになりました。教室にはエアコンがありましたが、特別教室にはありませんでした。電気がくる前は、仮設トイレのための照明とかが必要なので、建設会社から持ってきた発電機を2機置いて照明に使いました。
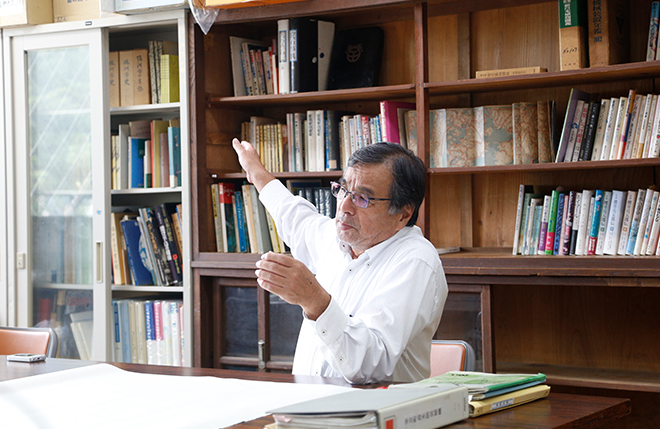 宝立公民館でインタビューに応じる多田さん(2024年9月19日撮影)
宝立公民館でインタビューに応じる多田さん(2024年9月19日撮影)
避難所をどのように運営したか
- 聞き手
-
避難所はどのように運営したのでしょうか。
- 多田さん
-
一番気を使ったのは、やはり見知らぬ人ということです。ほとんどが宝立町内の人でしたが、町内でも本当に隣の人だったら分かりますが、通りを越えて、隣の地区の人と一緒に避難生活することになります。1月2日、正式に避難所として運営本部を立ち上げ、責任者も決めて、ここで運営を開始しますということを、各グループの責任者がいなかったので、私と区長会の副会長と2人で、全部の教室を回り、当面のことをお伝えしました。誰かが中心となり、やはり組織的に動いていくことが必要でした。みんなバラバラになると、烏合の衆になってしまうので、運営本部がきちっと動いて、避難している人が安全安心に過ごせるように協力してくれとお願いしました。ここは1人1人の家と違います。いろんな人が集まってきているから、協力しないと大変なことになるし、自分のやりたいこと、したいことは、避難所だから我慢してくれとお願いしました。
そして、最初にお願いしたことが、各グループでリーダーをつくることです。例えば、多目的教室に集まっている人、図書室に避難している人、それからランチルームに避難している人など、約20グループほどありました。それぞれのグループにリーダーをつくりましょうと呼びかけました。一番大事なことは何だろうと考えた際、避難者が不安になるのは、情報不足になることだと思いました。正確な情報を伝えようと、役所との連絡も携帯も全然通じない時もありました。役所でも防災本部を立ち上げるのに時間がかかります。道路が寸断されているので、職員がなかなか集まってこないという状況もあったので、できる限り正確な情報を、まずどうやって伝えるか、そのことがとても一番大事だと考えました。最近では、SNSとか非常に便利なものがあるけれど、私はSNSって本当に大丈夫なのかと思っています。確かに、ライブで映像を流しているのを見ると、そうなのかって分かるけれど、1人1人が解釈して、1人1人の感情を入れながら次の情報を作っていくから、結構当てにならない情報がたくさんあります。そういう情報を見て、一喜一憂してもらうのが一番困るので、まずグループごとにリーダーを作ってくれと、リーダーはある程度責任を伴うので、そうした呼び方をすると誰もならないので、リーダーという言葉は使わず、情報連絡係を作ってくれと言いました。情報連絡係を通じて各グループの方に、「正確な情報は、本部から出る情報です。これは我々が紙で役所から得た情報です。それをきちっと皆さんにお伝えするから、これだけは信用してくれ。他はしばらく信用しないでくれ。」と伝えてもらいました。流れとしては、1月から3月までは、朝9時、夕方4時に、情報連絡係に集まってもらい、その時その時で大事なことを、そこで連絡しました。
その後、食べることも心配だったので炊き出し要員、それから炊き出しを学校の駐輪場を改造して行わなければいけなかったので、日曜大工が得意な人、あとは仮設のトイレ管理する人とか、そういう係をつくり、全体が少しずつ機能できるように、安心安全で過ごしてもらえるように、そういうことを本部として行いました。もちろん本部も、しばらく私が本部長でしたが、「私が倒れた時は、誰か私の代わりになってくれ。」と言って、サブを作り組織として運営していましたし、自衛隊のお風呂が設置された際は、例えば、どこを控え場所にするかとか、どうしたらうまくみんなに入ってもらえるかということで、お風呂の担当も作りました。最初は短時間で回すため、1人20分、3日に1回という数字をお風呂担当者が計算して出してくれました。
1月8日にコロナの1人目が発生しました。ただし、6日に常駐の医療チーム(HuMA災害人道医療支援会)が入ってくれたので、医者と看護師の方、医者の方が1、2名ないし看護師の方が6名常駐してくれたので助かりました。1月中旬には、避難者が240名から300名いましたが、そのうち最大で50名近くがコロナに感染しました。隔離しなければいけないので、陽性となったら、すぐ隣の県立の特別支援学校に頼み、特別支援学校の2階の部屋を全部開放してもらいました。ちょうど冬休みで、子どもたちもいなかったので全部開けてもらい、布団とかダンボールベッドを設置しました。我々の本部でも、地元の看護師が4人ほど避難していたので、もし何かあった時には頼むねと伝えていました。そういう医療チームもつくりました。避難所の運営というのは、大まかにそんなところです。
初期対応が一番難しかったです。誰もそんなやったことがないし、グループの責任者をどうするかということもありました。幸い、責任者の方から、「情報連絡係では、『重み』がないので、責任が伴うような名称に変えてもらえないか。」と言われたので、「それでは、リーダーにしよう。」となりました。中には「いや、私は情報連絡係のままにしてください。」と言う人もいました。「それはそれでいいよ。」と伝えました。最初の頃、頭に浮かぶ大変なことは、そんなところです。
避難所生活で一番困ったこと
- 聞き手
-
避難所での生活で一番困ったことはなんですか。
- 多田さん
-
やっぱりトイレです。下水も上水も断水していたので、学校のトイレは全て大便で埋まっていました。あとは簡易トイレ、災害用の段ボールの簡単なトイレを使い、ビニール袋の中に凝固剤を入れてやっていました。かなり大変な状況でした。その時に救いの神がいるのだと思った出来事があり、1月2日に静岡県から下水道管の管工事をするボランティアの社長が来てくれました。とても立派な方で、その人は阪神淡路大震災で被災した教訓として、トイレのことを心配していました。その人が来て、「今困っていることは、トイレだろう。」と言って、仮設トイレができる前にマンホールトイレを作ってくれました。スタッフが囲いと、屋根を作ってくれました。これだとストーン、ストーンと落ちていくから思いっきり用を足すことができました。最初は、それでクリアできたのですが、和式の仮設トイレはお年寄りにとって非常に難しいようで、足腰が弱っているのでバランスを崩してなかなかできず、トイレの中でひっくり返って衣服を大便で汚してしまう方もいました。
他県の支援でトレーラートイレが入ってきて、エアコン付きでウォシュレットも温かく、自治体独自でつくり、どこかが被災した時にそれを持っていき、貢献しようということで、勉強させてもらいました。このトイレもすごく進化しており、トレーラートイレは6ヶ月間いて、日本の技術は、すごいと感じました。 宝立小中学校に設置されたトレーラートイレ(2024年1月26日撮影)
宝立小中学校に設置されたトレーラートイレ(2024年1月26日撮影) - 聞き手
-
将来こういう事態が起こった時に、避難所の運営とか、設備とかでどういうことがあったら望ましいと思いますか。
- 多田さん
-
食料とかを備蓄するのはもちろんだけれど、避難所を誰がどう運営していくのかが大事です。避難する人は恐怖体験をして、身内がなくなっている方もいて、この地域でも大体28人が亡くなっています。精神的にすごくダメージを受けている人もいるし、家の下敷きになってやっと抜け出して助かった人もいる。すごい恐怖体験をして、とにかく逃げようとここに集まってきて、振り向いたら知らない人が横にいて、そういう精神状態の人間が避難している中で、安心安全に運営するにはどうすればいいのか。3日とか1週間くらいならなんとかなると思いますが、8ヶ月もそういう生活を続けるのは、すごいストレスになります。途中で仮設住宅に入る人もいて、避難所の中にも変化があります。色々なストレスを抱えている中で、そうした人間にどう安心して避難生活をさせるのか非常に難しいことです。だから、そういう不安を払拭するためにも、どんな運営をするかが非常に大きなこれからの課題だと思います。たまたま自主防災組織というものがあったので、勝手に解釈して避難所は自主防災組織でやるものだと思いながらも、本当はどうなのかなという気持ちもありました。これは事前に、その地域の風土とか色々な組織があると思うので、その地域でもし長期にわたる避難所を運営しなければならなくなった時に、誰が中心になって、どうやるのかということを決めておくことが大切です。
要介助者への対応
- 聞き手
-
要配慮者の方への対応はどのような感じだったのか教えてください。
- 多田さん
-
要介護の人が(避難所に)入ったらダメだとは絶対に言えないし、入ってから要介護と分かることも多かったです。床に寝るのは良くないので、高齢で足の不自由な人には、もっともっと先にダンボールベッドを入れてあげるべきだったと思っています。
脳梗塞の人も避難してきました。避難してきたけれど、やはり避難所で過ごすのが難しく、自衛隊の力で名古屋の方の病院に入院していただきましたが、「やっぱり都会の病院は嫌やった。こっちに帰りたい。」と言って、そこの主治医が私に電話をかけてきて「帰りたいって言っているんですが、避難所はどうですか。」と相談されました。「避難所ってどういうところか知っていますか?対応できません。」と伝えました。ただし、お母さんは元気で「お父さんのことを世話できます。半身が不自由なので大変ですが、世話をします。」と言っておられましたので、承認して帰ってきました。やっぱりメンタルな部分でふるさとを離れるっていうのは非常に負荷がかかるみたいです。だから、多少不自由な生活でも、病院より避難所の方がいいなんて、そんな馬鹿な話はないと思いましたが、避難所に帰ってきたら近所の人がみんな声をかけてくれて、病院も大事なのですが、そういうメンタルの部分をカバーしていくときにやっぱり近所の人の力ってすごいと感じました。
それから医療チームとの相談体制が非常に良かったです。後で分かったのですが、知的障害で少し難しい方もいて、医療チームの精神科医に相談したら、「この人は個別の部屋がいいですよ。」と言われました。そこで、コロナ患者が2階で、その人は3階に移動してもらいました。医療チームからは「避難所として対応が非常に難しい場合は、相談してくださいね。」と言われ、結局また相談したら、今度は石川県の心の病院に受け入れしてもらえました。だから、要介助者については本当に外部と結構連携が取れていたので、比較的遅い部分もありましたが対応はできたと思っています。自衛隊風呂ついては、自衛隊と相談して、13時からスタートだったけれど、12時半から要介助者と家族のために、自衛隊風呂を開放するという対応をとってもらいました。
色々な人間がいて、どう対応するかといった時に、外部の色々なグループ、看護師・保健師チーム、医療チームときちっと連携することが出来たということは、運営上、非常に大事だったと思っています。看護師チームからは、段ボールベッドも高齢者には有効と言われ、高齢者から先に入れました。その後、医療チームから、もしノロウイルスが出てきたら、床で寝ていたら大変なことになると言われ、その時に一気に300近くの段ボールベッドをみんなで使うことにしました。班長を集めて、ノロウイルスが入った時に、どう対応するかということを2、3回くらい講習しました。結局ノロウイルスは出ませんでしたが。食料とか物品の支援チームもありましたが、医療チームとの連携も重要でした。
避難所運営と子どもたち
- 聞き手
-
子どもがいることで揉めたことってありますか。
- 多田さん
-
小さい子もいたし、小学生、中学生、高校生もいました。小さい子がいるからうるさいとか、そうした声はあまり出ませんでした。避難所は、小さな子ども、小学生とか保育所を持っている人たちをできるだけ一箇所に集めました。それから、休みとか冬休み中は、中高生は積極的に避難所運営に関わってもらいました。物資を支給したりするコーナーに立ってもらい、例えば、絆創膏をくださいと来る方に対応してもらいました。最初はスタッフも立っていましたが、校長と相談して、中高生にそこに立ってもらい、どの物資がどこにあって、誰かが注文してきたらこれをあげてくださいとか、館内放送についても、子どもたちに対応してもらいました。
 宝立小中学校の体育館に集まった物資(2024年1月26日撮影)
宝立小中学校の体育館に集まった物資(2024年1月26日撮影) - 聞き手
-
小中学校はいつから再開したのですか。
- 多田さん
-
1月22日です。その前も非公式で集まり、自習をしていたみたいです。学校再開に伴い必要な教室を空けなければいけないので、そこに入っている避難者には移動してもらい、1フロアを全部開けました。
- 聞き手
-
小学校、中学校の運営と避難所の運営を両立していく上で、特に工夫したことはなんですか。
- 多田さん
-
校長には「しばらく同居する生活で、色々迷惑かけたりすることもある。」と伝え、2人の間で「こういう状況を体験することも、子どもたちにとってはとても良いことだし勉強になる。」と話をしていました。いつも言っていたのは、避難者に対して、「子どもたちが一緒にいるんだよ。本当は子どもたちの学校なんだよ。たまたま、私たちが借りているんだよ。宝立のこれからを担っていく子どもたちが宝立の大人の姿をずっと見ていますよ。だから下手なことをしないでください。」と伝えていました。そういう意味で、お互い相互作用ではないけれど、子どもたちの力というのも大きかったです。一緒に生活する中で、子供たちから力をもらったこともあったし、校長がそういう意味で机上の勉強も大事だけれど、こういった体験を通じて、地域のために貢献していくことがとても大事だという話をしました。
皆さんへのアドバイス
- 聞き手
-
最後にアドバイスはありますか。
- 多田さん
-
私が勉強になったのは、色々な若手がいることです。自主的に来てくれて手伝ってくれた若者がたくさんいました。困っているのだから、地域のために何か手伝うことはないかと集まってくる若者がいました。そういう若者を引き出していく、見出していくこともとても大事だと思いました。
運営の本部というか、スタッフがきちっと機能することは非常に難しい。みんな素人なので、たまたま区長していたから呼ばれて、ここにいますが、みんな前向きに色々なことを一生懸命考えてくれました。最初は避難者を大事に、大事にしていたけれど、運営側の我々も被災しているんだよと、いつまでも大事に、大事にではなくて、トイレ掃除にしても、道の掃除にしても、部屋の掃除にしても、これはやっぱり避難者全員でやりましょうと伝えました。だから、要はチームとしてどう機能していくか、これは非常に難しいのですが、起こった時に最低でも誰がどういう組織をつくり、避難所を運営していくかということを、3、4日くらいだったら決めなくても良いと思いますが、これだけ長くなるとは思わなかったので、そうしたことを決めることが大事だと考えています。地域によっては、違う形態で避難所を運営されていると聞いたことがありますが、宝立町は一応自主防災組織があったので、それを拡大解釈して運営しました。
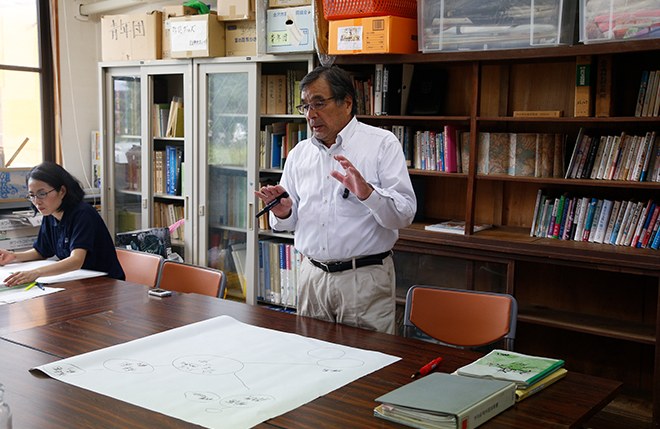 当時の対応をしっかりと記録し、経験や教訓等を次の災害に活かそうとする多田さん(2024年9月19日撮影)
当時の対応をしっかりと記録し、経験や教訓等を次の災害に活かそうとする多田さん(2024年9月19日撮影)
伝える
- 体験を語る
-
県民
-
学校
-
企業・団体
-
関係機関が作成した体験記録

